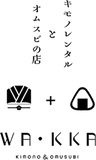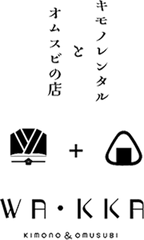🌼例年の見頃:2月上旬~3月上旬🌼 写真:京都フリー写真素材
キモノレンタルとオムスビのお店 WA・KKAの「京都・梅の名所|着物散策ガイド」Vol.1は、京都最古の神社の一つであり、世界文化遺産にも登録されている「下鴨神社(しもがもじんじゃ))」のご紹介です。
その歴史は古く、創建は不明ですが、平安京遷都以前から存在したとされています。下鴨神社の境内には「光琳の梅」と呼ばれる紅梅があり、江戸時代の画家・尾形光琳(おがたこうりん)が描いた「紅白梅図屏風(こうはくばいずびょうぶ)」に描かれた梅として知られています。 光琳の梅は、その鮮やかな紅色と独特の枝ぶりが特徴で、多くの人々を魅了してきました。また、下鴨神社は、梅の花だけでなく、境内の自然や建築物も美しく、写真撮影のスポットとしても人気があります。
おすすめ! 着物で撮影はここ

写真:京都フリー写真素材
下鴨神社を着物で散策した際に、梅の花を背景に撮影するなら、光琳の梅と朱色のコントラストが映える「輪橋(そりはし)」がおすすめです。また、下鴨神社のシンボルともいえる「楼門(ろうもん)」も外せません。
輪橋
輪橋は、下鴨神社の境内にある御手洗川(みまた、たらしがわ)に架けられた朱塗りの美しい反り橋です。橋の形が車輪に似ていることに由来し、別名「太鼓橋(たいこばし)」とも呼ばれています。橋が架かっている御手洗川は、普段は水が流れていませんが、土用が近づくと水が湧き出てくることから、「京の七不思議」の一つとされている川です。輪橋は、神域と俗界を隔てる結界の役割を担っていたと考えられ、神輿や祭りの行列が渡る橋としても使用されていました。その美しい姿は、下鴨神社の風景に彩りを添えています。
楼門
楼門は、下鴨神社のシンボルとも言える朱塗りの二層楼門です。入母屋造、檜皮葺の屋根をもち、高さが約13メートル。寛永5年(1628年)に造替されたもので、国の重要文化財に指定されています。楼門は、神社の正門として、参拝者を迎える役割を担っています。
下鴨神社について
下鴨神社は、京都最古の神社の一つであり、正式名称は「賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)」です。 古代より、この地は神聖な場所として崇められてきました。 下鴨神社は、平安京遷都以前から存在し、皇室や貴族からも崇敬されてきた神社です。 京都三大祭りの一つである「葵祭」の舞台としても知られています。 境内には、国宝の本殿や重要文化財の楼門など、数多くの歴史的建造物があり、糺の森と呼ばれる原生林も広がる、歴史と豊かな自然を楽しむことができるスポットです。
アクセス情報
- 所在地:京都市左京区下鴨泉川町59
- 交通手段:京都市営地下鉄烏丸線「北大路駅」または「今出川駅」から徒歩約15分、または京都市バス「下鴨神社前」下車すぐ
- 公式サイト: https://www.shimogamo-jinja.or.jp/
お店から下鴨神社へは、京都市バスで約30分です。
下鴨神社の梅の見頃
下鴨神社の梅の見頃は、例年2月下旬から3月中旬頃です。この時期には、光琳の梅をはじめ、境内の梅の花が咲き誇り、訪れる人々を楽しませます。 ご紹介しました、楼門と輪橋は、下鴨神社の歴史と文化を今に伝える貴重な建造物です。訪れた際には、ぜひ、その美しさを間近で感じてみてください。